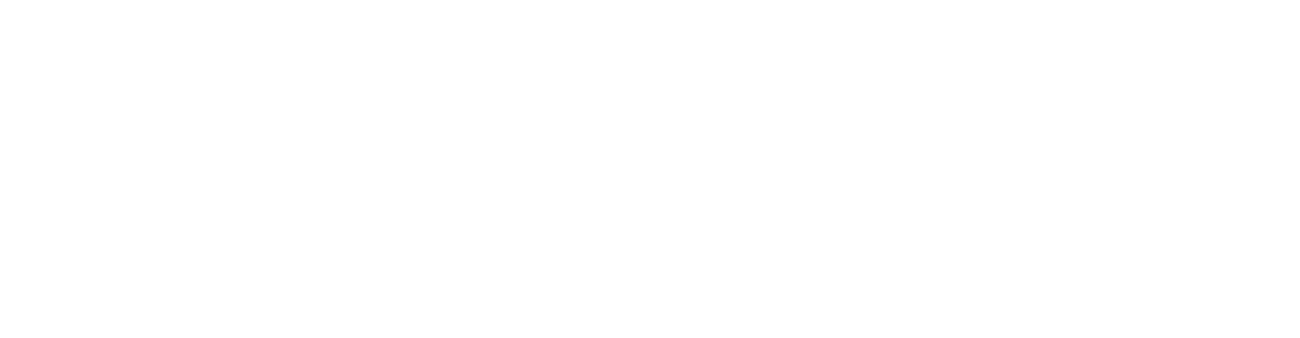はじめに -ブラチスラバと私
こんにちは、6Gテック部 アーキテクチャ標準化担当の土尻です。
2025年5月の私の担当する3GPP CT4会合は、ブラチスラバで開催されました。ブラチスラバは、ドナウ川沿いに位置し、オーストリアとハンガリーに国境を接するスロバキアの首都であり、豊かな歴史と活気ある文化を持つ都市です。都市が持つ魅力だけでなく、実はこの街は重要な3GPP会議を何度も主催しています。3GPPサイトによると2010年から30会合ほど開催されているようです。3GPPの関係者にとっては”第二の故郷”ともいえるかもしれません。私自身にとっても今回が2度目のブラチスラバ。標準化に携わって3年になりますが、毎回多くの学びがあります。今回は、3GPP CTにフォーカスした内容をお伝えします。ぜひ最後までお付き合いください。

3GPPとCTの役割- 縁の下の力持ち、されど超重要!-
3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、移動体通信システムの技術仕様を策定する国際標準化プロジェクトです。3GPPは大きくTSG(Technical Specification Group)と呼ばれる以下の主要な3つの技術仕様策定グループで構成されています。
- RAN(Radio Access Network:無線アクセスネットワーク)
RANは無線アクセスネットワークの設計、要は端末に向けてどうやって電波を吹くかを検討する無線サービスの「花形」です。 - SA(Service and System Aspects:サービスとシステム)
無線も含めたネットワーク全体の設計図を描く「建築家」です。 - CT(Core Network and Terminals:コアネットワークと端末)
CTは設計図に基づき通信システムを作り上げるいわば「匠」といった感じです。

さらに、各TSGの配下にサブグループがあり、それぞれ決められた業務範囲において標準化活動を行っています。私が所属するCTグループは、特にコアネットワークと端末間をつなぐ通信使用を細かく定める極めて実務的かつ重要な役割を担っています。
3GPPの組織構成や標準化の流れに興味のある方は、弊社石川の3GPP副議長就任時のブログ※1や3GPP公式サイト※2の「3GPP Groups」タブにあるToR(Terms of Reference:業務範囲)をご参照ください。すべてのTSGグループの活動概要が記載されており、最も厳密で正しい情報です。実際の会合においてもToRが議論のベース資料として資料されることが多く、信頼できます。
CT4の標準化活動 - 実運用と標準化をつなぐ-
CTグループは、主に移動体通信ネットワークのコアネットワークおよび端末に関するプロトコル仕様の策定を担っています。具体的には、端末とコアネットワーク間のインターフェース、コアネットワーク要素間のインターフェースの定義、およびこれらのインターフェースにおけるシグナリング手順やデータパスの確立に関する詳細な仕様を策定します。移動体通信システムがエンドツーエンドで円滑に機能するための基盤を形成するものであり、その役割は極めて重要なものです。
これらをCTのサブグループであるCT1, CT3, CT4, CT6が分担して標準仕様を策定しています(CT2とCT5が存在しない不自然さについては歴史的な背景によるものと思われます)。
CTグループの仕様書は、通信機器の開発に直結するため、ベンダーからの参加者が多くみられます。一方で、私たちのような通信事業者が参加する意義は、実際のネットワーク運用経験における課題や制約といった知見を標準仕様に反映できる点にあります。これは、あんしん・安全なネットワークの構築・運用のためにも非常に重要になります。
また、CTは開発に近いところにあるため、一度リリースが凍結しても継続的に使用の改善作業が続く特徴があります。主にバグ対応や”準正常動作”が要因となるため、改善自体は素晴らしいことですが、同時に仕様が変わると運用に影響が発生する場合もあります。そのため状況を注視し、場合によっては通信事業者としての意見を表明しなければなりません。
こうした現場のバランスを取る場所として、CTは「世界の通信の未来」と「実運用」を"つなぐ場所”とも言えるかもしれません。たとえば、CT4にてRel-18で規定された「カナリアリリース」※3という仕組についてです。これは、新しいバージョンのソフトウェアを一部のユーザーやデバイスに限定的にリリースすることで、バグや互換性の問題が発生した場合でも、その影響を限定的なユーザーまたはデバイスに留めることを可能とする機能です。機能自体に派手さはないかもしれませんが安定した実運用にとっては有効な手段の1つになり得ます。
会合を通じた気づきと学び - 技術と議論の現場から-
ブラチスラバへ。温かいもてなしをありがとう。
会合期間中、すべての技術的な詳細な複雑さを完全に理解できたとは言えませんが、会合参加を通して標準仕様についての理解がさらに深まったと思います。
今回特に印象的だったのは、ローミングへの考え方について、他オペレーターと活発な議論が起きたことです。会合中の意見の違い、価値観の違いによる議論は(私にとっては)ストレスを伴いますが、それもまた貴重な経験であり、同時に自分自身にとって大きな勉強になります。機会があればまた技術仕様へのより深い理解およびイノベーションへの強いモチベーションを携えて、この地に戻ってきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。

もっと知りたい方へ – 参考リンク集
3GPPに興味を持たれた方のために、参考になりそうなリンクをご紹介します。
※1 3GPPの副議長に当選した話 - ENGINEERING BLOG ドコモ開発者ブログ
※2 3GPP – The Mobile Broadband Standard
※3 3GPP Release 18における5GCの高度化技術概要―コアネットワークと端末― | 企業情報 | NTTドコモ